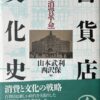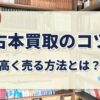ISBNコードとは?書籍の識別番号の意味と役割を解説
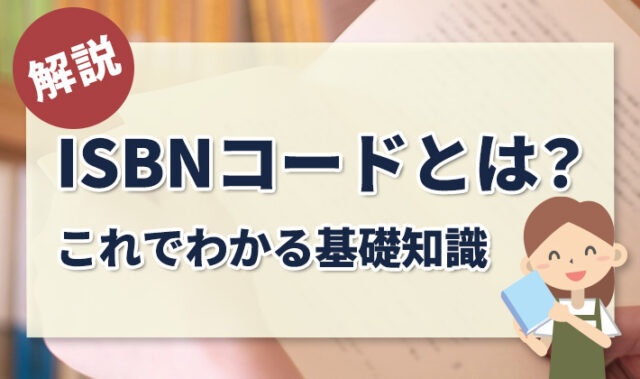
書籍の裏表紙に記載されている「ISBNコード」という文字列をご存知でしょうか?このコードは、書籍を特定するための世界共通の番号です。本記事では、ISBNコードの仕組みや役割、さらにその歴史について詳しく解説します。
ISBNコードとは?
「ISBNコード」という言葉を耳にしたことがない方でも、本の裏表紙にあるバーコードを見たことがある方は多いでしょう。そのバーコードの下に記載されている13桁の数字が「ISBNコード」です。この番号は書籍を特定するために付与されるもので、出版物の流通や管理に欠かせません。
国際標準図書番号(ISBNコード)の意味と役割
ISBNコードとは、
「International Standard Book Number」
(インターナショナル・スタンダード・ブック・ナンバー)
の略称で、日本語では「国際標準図書番号」と呼ばれています。これは書籍を世界的に識別するための番号体系であり、一冊ごとに異なる番号が割り当てられています。書店や出版社、図書館などが書籍の管理や流通を効率的に行うために欠かせない仕組みなのです。
この番号があることで、同じタイトルや似たような内容の書籍が多数存在する中でも、正確に特定の書籍を識別できます。また、出版業界全体で統一された規格を採用することにより、書籍の注文や在庫管理、データベース登録などの業務が円滑になり、流通過程の効率化やトラブル防止にもつながっています。
なぜISBNは誕生し、普及したのか?
ISBNコードが生まれた背景には、1960年代における書籍市場の急激な拡大があります。当時は国ごとに書籍の管理番号が異なっており、国際的な書籍流通や管理が非常に煩雑でした。その状況を改善するために、1967年にイギリスの出版社団体が統一した番号システムを提唱しました。これがベースとなり、1970年に国際標準化機構(ISO)が正式に「ISO2108」として承認したことで、国際的な規格として広まりました。
日本では1981年から本格的に導入が開始され、その後書籍の出版点数が増えるにつれISBNコードの普及が進んだのです。現在日本のISBNコード取得は、日本図書コード管理センターが行っています。ISBNコードの取得は義務ではありませんが、書籍の流通、管理の効率化などの理由により、ほとんどの出版物でISBNコードが付与されています。
当初は10桁でしたが、2007年から現在の13桁形式に変更されました。この変更によってより多くの出版物を管理できるようになり、現在では200以上の国と地域で利用されています。
ISBNコードの仕組み
ISBNコードの構成
ISBNコードは単なる識別番号ではなく13桁の数字が複数のセクションに分かれており、セクションごとに異なる情報を表しています。それぞれの部分がどのような意味を持ち、どのように書籍を特定する役割を果たしているかについて詳しく見ていきましょう。
まず、13桁の数字は以下の順番で記載されています。先頭から順番に解説します。
接頭記号「978」-国記号「4」-出版社記号-書名記号-チェックデジット
- 接頭記号
- ISBNコードの最初の3桁は「978」または「979」で始まります。これはEAN(国際商品番号)システムに統合されており、この数字が書籍であることを示します。現在、日本のほとんどの書籍は「978」が使用されていますが、将来的には「979」への移行が進むとされています。
- 国記号(グループ番号)
- 書籍が出版された国や地域を示す番号です。日本の場合は「4」が割り当てられており、「978-4」のように表記されます。
- 出版社記号
- 国記号の後には、その国や地域内で出版社を特定するための番号が続きます。出版社記号は出版社ごとに異なり、規模や出版点数によって2桁から7桁で異なる番号が割り当てられます。
- 書名記号
- 出版社記号の後には、その出版社内で出版された書籍を個別に識別するための番号が続きます。1桁から6桁までありますが、出版社記号と書名記号の合計桁数は常に「8桁」となるように調整されます。
- チェックデジット
- 最後の1桁はチェックデジットと呼ばれるもので、ISBNコード全体が正しく入力されているかを確認するための検証番号です。モジュラス11という計算式を用いて算出されるため、入力ミスや誤植を防ぐ役割を果たします。
これらのセクション分けにより、ISBNコードは世界中で書籍を特定し、出版社や販売者、読者にとって非常に便利なものとなっているのです。
日本独自のCコード(分類記号)システム
「C○○○○」のように、Cから始まる4桁の数字は図書館などで見かけることも多いのではないでしょうか。日本ではISBNコードのほかに独自の書籍分類システムとして「Cコード」があります。これは書籍の内容や読者対象、判型を示すために、日本独自に制定された4桁の数字で構成され、以下のように「販売対象」「発行形態」「内容」の3つの要素で分類されています。それぞれの要素がどのような意味を持つのか、まとめました。
販売対象(第1桁)
| コード | 意味 |
|---|---|
| 0 | 一般 |
| 1 | 教養 |
| 2 | 実用 |
| 3 | 専門 |
| 4 | 検定教科書・消費税非課税品・その他 |
| 5 | 婦人 |
| 6 | 学参Ⅰ(小中学生対象) |
| 7 | 学参Ⅱ(高校生対象) |
| 8 | 児童書 |
| 9 | 雑誌扱い |
発行形態(第2桁)
| コード | 意味 |
|---|---|
| 0 | 単行本 |
| 1 | 文庫 |
| 2 | 新書 |
| 3 | 全集・双書 |
| 4 | ムック・カレンダー・日記・手帳・その他 |
| 5 | 辞典・事典 |
| 6 | 図鑑 |
| 7 | 絵本 |
| 8 | 磁性媒体など(CD-ROMなど) |
| 9 | コミックス・劇画 |
内容分類(第3・4桁) – 一部抜粋例(詳細はさらに細分化されています)
| コード範囲または番号 | ジャンル/内容分類例(大分類と中分類) |
|---|---|
| 00~09 | 総記(百科事典、年鑑、情報科学など) |
| 10~19 | 哲学心理宗教(哲学、心理学、宗教、仏教、キリスト教など) |
| 20~29 | 歴史地理(日本史、外国史、伝記、地理、旅行など) |
| 30~39 | 社会科学(政治、法律、経済、教育など) |
| 40~49 | 自然科学(数学、物理学、化学、生物学など) |
| 50~59 | 工学工業(土木、建築、機械、電子通信など) |
| 70~79 | 芸術生活(絵画彫刻、音楽舞踊、演劇映画など)コミック含む。 |
Cコードを見ることで、書店や図書館などで、自分の探しているジャンルの本を見つけやすくなります。例えば、C3041と記載されている本は、専門的な数学書であることが分かり、目的の本を探しやすくなります。
また、ISBNコードと併せて記載することにより、日本国内での書籍流通がより効率化されます。
発行形態によって違う?ISBNコードの基準
ISBNコード付与対象の書籍
ISBNコードは基本的に、出版され流通する書籍やパンフレット、冊子などに付与されます。具体的には以下のようなものが対象です。
- 書店で販売される単行本・文庫・新書など一般書籍
- 自費出版や少部数出版でも流通を伴う場合
- オンデマンド出版で紙媒体として販売される書籍
- 教科書や参考書など教育用書籍
基本的に書店流通する紙媒体の書籍には、すべてISBNコードが付与されることになります。
ISBNコード対象外の書籍(ISMN・ISSN)
一方、ISBNコードとは別の番号体系で管理されている出版物も存在します。たとえば、楽譜などの音楽関連の出版物にはISMN(国際標準音楽番号)が割り当てられ、雑誌・新聞などの定期刊行物にはISSN(国際標準逐次刊行物番号)が付与されます。
- ISMN
- 楽譜・音楽書籍を管理するための国際規格番号で、「979-0」から始まる13桁の番号です。
- ISSN
- 定期的に発行される雑誌、新聞、学術誌などに割り当てられる8桁の番号です。
これらの番号は書籍(ISBNコード)と明確に区別されており、同一の出版物にISBNコードとISSN・ISMNの両方が付与されることはありません。
ISBNコードが不要な書籍
ISBNコードは紙媒体の書籍に対して広く使われていますが、電子書籍の場合には必ずしも必要ではありません。電子書籍はオンラインストアごとの識別番号や独自のIDで管理されるケースが多く、ISBNコードが付与されない場合もあります。ただし、紙書籍と電子書籍が同一タイトルとして販売される場合、識別のために電子書籍版にも別途ISBNコードを付与するケースもあります。
電子書籍の市場が拡大している中で、ISBNコードの必要性については出版元の方針や流通経路によって異なっています。
長島書店ではISBNコードのない古書でも買取可能です
古い時代に出版された書籍や特別な書籍にはISBNコードが付いていないことが多くあります。特に、ISBNコードが導入された1981年以前に刊行されている書籍にはISBNコードが付与されていないものが一般的です。そうしたISBNコードがない書籍でも、古書市場では価値を持つものが多数あります。
ISBNコードの有無だけで書籍の価値が決まるわけではなく、書籍の希少性、歴史的価値、保存状態などが査定の重要なポイントになります。そのため、古書店や専門の買取店ではISBNコードがない書籍であっても十分な査定・買取が行われています。
まとめ
ISBNコードとは書籍を世界共通で識別・管理するために作られた規格番号であり、流通を効率化するために欠かせない仕組みです。日本ではさらに独自のCコードを加えることで、より細かい分類が可能となっています。
一方で、ISBNコードが存在しない書籍でも、特に古書の世界では査定対象としての価値を十分持ち得ます。古い書籍を売りたいとお考えの方は長島書店のようなISBNコードがなくとも買取可能な店舗へ相談することをおすすめします。
お問い合わせ
売りたいお品をお伝えいただけましたら大よその買取金額をお調べ致します。

お電話からのお問い合わせは
0120-414-548
受付時間:平日10:30~18:30定休日:日曜・祝日